
このところ関西方面では、kenjiさんの影響で(笑 めきめき人気のルシアーさんです。 今回は幸いにもいろいろとお話をお伺いできましたので、なにはともあれ。 今回お持ちになった3本です。カッタウェイが2本と、ノンカッタウェイですね。 一番手前は、シトカにローズ。口輪がアバロンのものです。もう一本のニレコブのロゼットはイングルマン。 ノンカッタゥエイはシトカにマホガニーです。どれもすっきりした、きれいなデザインですね。

古谷さんはトップ構造の剛性を、「中心が弱く、周りに行くにつれて剛性が上がる」という考え方で 進めているそうです。トップ全体は、音源となるブリッジ周辺をもっとも軽くし、周辺に行くにつれて強くなる ように作るそうです。これは、わたしが考えるに振動のもっとも大きいところをもっとも敏感にすることで 倍音をより豊かにする工夫ではないかと思います。もちろん周りの剛性が上がると言っても、振動を抑制する ようには作られていません。トップは、大きなアールの頂点にブリッジが来るようにしてあるため、 ブリッジにかかる弦のテンションをうまく周囲に応力分散させることで十分な剛性を得ることができる そうです。わたしがイメージしたのはスピーカーユニットの(またスピーカーかよ!w)センターコーンです。 よくスピーカーの中心には金属のドームがくっついていますが、この直径と同じだけの「ボイスコイル」という 筒がその下へ伸びています。これが前後することによってスピーカーユニットを駆動するのですが、 このセンタードームのあるなしで高域周波数が軽く2000ほど上下します。高音域には都合のいい構造ですが、 古谷さんのギターは、いわばトップ全体がそのような運動をすることで、豊かな倍音を作り出しているのかも しれません。 い、、、いや、マジわからんけどね(笑。 それと、サイドのラミネートについてお伺いしたところ、「サイドは固めない方が好み」とのこと でした。サイドをラミネートするより、多少動いても良いから単板のサイドが振動する方が、自分の考えに 沿った構造だと言うことでした。わたしも、どちらかが良いというものではないと思っているので、 音づくりの上で自分の方向性に合っているなら、どちらでも良いと思います。

まずはきれいなニレコブのロゼッタです。コブ関係は(笑、ニレの他にカリンやメイプル、クスノキなどが 有名?です。あっちでは「バールなんとか」と呼ばれて、ソモギもヘッド裏に使ったりしていますね。 大きな部材がとりにくく、収縮がランダムでしかも大きいので構造材としては使いにくい部位です。 しかしこうした装飾に使われると、非常にきれいで高級なイメージが出ます。スポルティッドメイプルも 同様に美しい部材ですね。ルシアーの人はこれからもっとよく使うようになるのではないでしょうか。

とてもしっかりしたヒール形状です。わたしは素朴な質問をしてみました。ヒール端を四角くせず、 アーチ型にするとどうですか?というものです。かまぼこ型とでも言いましょうか。 すると明確なお答えをいただきました。まず、「ネックの削りを13Fくらいまでストレートに持ってきて いるので、ヒール部の剛性は確保したい。それには十分な厚みをとっておきたいことが一つと、10年後に ネックを抜かなければならないリペアが出るかもしれないが、そのときにかまぼこ型ではエッジ部の強度に 不安があり、押し抜こうとしたときに欠けるかもしれないので避けたい。また、デザイン上もかまぼこ型の ヒール端をネック部とのスムーズなアールでつなぐことは、今のデザインだときれいにつなげそうにない。 ネック部の削り込みを浅くすればできるかもしれないけど、それでは演奏性が落ちるかもしれない。」 というようなことでした(要約あり)。ホント、非常に細かなことまで考え抜かれたデザインになっています。

今までも、微妙な変化をしながらの今の形状です。なかなか個性的で、一目で古谷さんとわかりますね。 ヘッドのつき板は秘密のルートからやってきた(笑、縞黒檀だそうです。国内調達。ペグはゴトーの 510クラスでしょうか。聞き忘れました(笑。デザイン上のポイントとして、このヘッドの長さと ブリッジの長さはほぼ同じになるようにしてあるそうです。これは、ギター全体のバランスを考えたとき、 そうするのが一番良いバランスになるからだそうです。ただ、ご存じのようにブリッジ長はもろに音に影響 します。見た目の形と音とのバランスは本当にシビアに決定しているそうで、細かい検証の積み重ねで 成立しているそうです。また、ブリッジ厚や重さ、スティッフネス等も様々なアイデアを加えています。
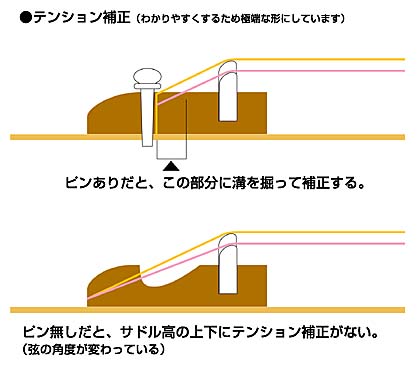


実は当日の会場は、かな〜〜り周辺の音が気になる状態で、この環境でいろいろ言われた日にゃぁ制作者として たまったもんじゃない!というのがおそらくは率直な印象でしょう(笑。そんな中での感想は、やはり倍音と きれいな伸びのある高音が記憶に残りました。狙ったとおりの音を実現できているのだと思います。 ホントのところ、静かなところで弾いてみたいですよ!kenjiさん!(笑。