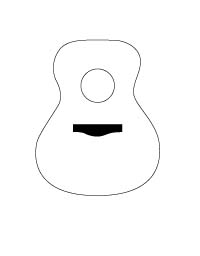
それぞれが重要な音の要素ですが、ここでは置いておいて、その後
トップの振動がサイドへ伝わる部分からはじめたいと思います。
トップは、振動することで音を作り出しますが、直接空気を振動させるのとともに、
ボディを振動させることで空気を動かします。また、ボディ全体も一つの球体音源と
して鳴り、ギターの音を形作っています。このとき、ギターのボディの動かし方に、
いくつかの考え方があると思います。

重要になります。この場合、小さいといえどサイドも振動することで音を作る方向です。
もう一つは、サイドを2P合板化することでできるだけ動かさないようにし、
トップの振動は空気媒介によってバックを動かす考え方です。
もちろん、どちらの場合でも空気によってバックは振動しますが、チャンバーとしての
空気圧でバックを動かし主に音量に関与する動きと、音の波によってバックを振動板、
反射板として動かす、音色に関する振動とがあります。反射板として考えた場合、
ボディ内の滞在波を考えねばなりませんが、その辺りはバックの項でお話しすると思います。
とりあえずサイドを考える場合、両方を考えなければなりません。

一つは、もっとも重要だと思うのですが、ボディ全体の変形が減る、ということです。
トップのうごきは、薄い木の集まりであるギターにとってはとても大きなものです。
トップの振動、変形につられて、ボディの形状もぐにゃりと動きます。
このとき、かなり多くのエネルギーが損失します。本来音に変換されて欲しい動きが、
変形することで損なわれるのです。すると、音量もサスティーンも減ってしまうことに
なります。2P合板化して剛性をあげることは、この変形を小さくすることができ、
音にとって有利な考え方ではないかと思っています。
もう一つは、トップの音の振動が、サイドからバックに伝わりにくくなることでしょうか。
多くの場合、固有振動数も比重も違う材との合板なので、単板の場合に比べて内部損失は
大きくなり、バックはその影響を受けにくく、より純粋に空気からの振動で動くと考えられます。
もちろん、これが「いいこと」なのかどうかは、考え方によるでしょう。
サイドからの振動をよりストレートに伝えたい、と考えた場合は、「良くない」事に
なるはずですから、そういう意図を持って作られたかどうかが大切だと思います。

そういうわけではないと思います。サイドが多少変形しても、単板が振動することで
音づくりに関与している場合、そのギターにとっては良い設計であるといえます。
サイドが振動して関与するパーセンテージは、きわめて小さなものと考えられます。
しかしながら、人間の耳は非常に微細な差を聞き分けることができ、
全く無駄な要素であるとは言い切れません。また、ボディ全体が変形することで
トップのストレスを緩和し、それがトップの振動にも関与している場合もあるので
どのような音づくり、方向性で設計するかが重要だと思います。
とりあえず今はここまで〜。